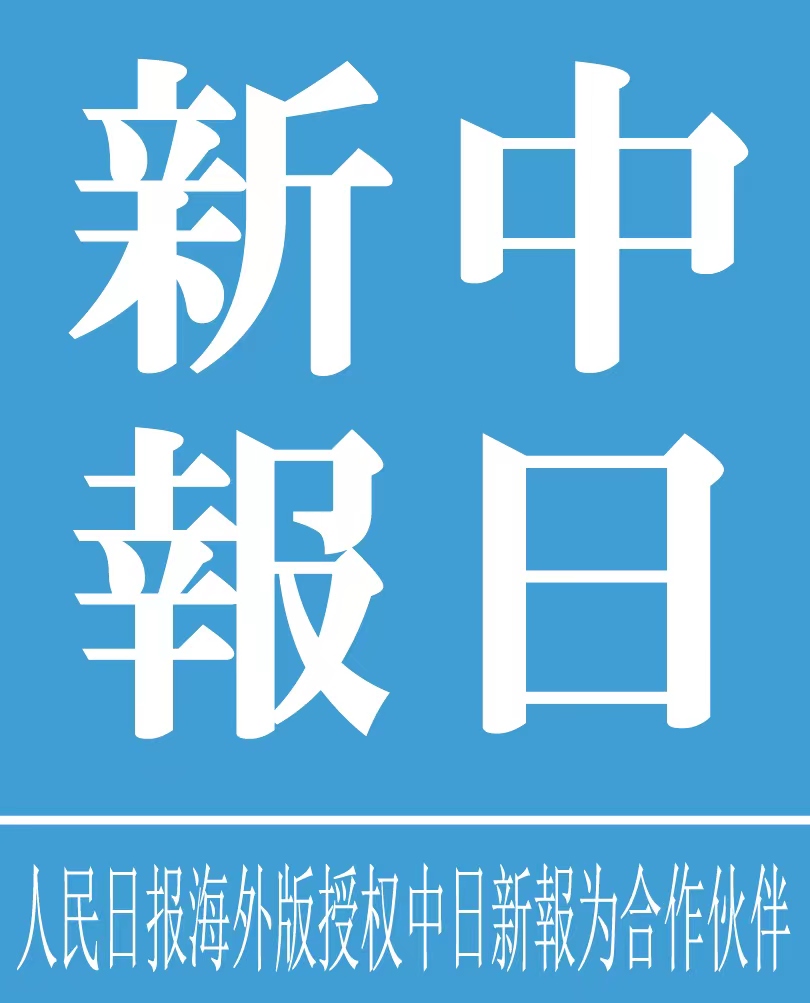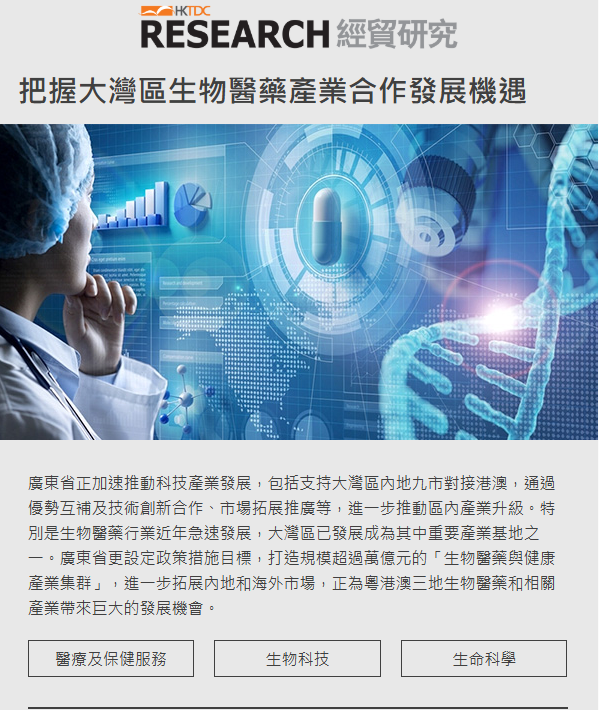把握大灣區生物醫藥產業合作發展機遇
|
香港の強固なビジネスプラットフォームを活用したASEAN・中国本土での事業拡大により関税の不確実性への対応を図る日本企業
2025年9月10日
香港貿易発展局 Galvin Chia Henry Cheung重要ポイント
• 主に中国本土(86%)、香港(78%)および ASEAN(70%)市場で調達・販売事業を行っている在香港の日本企業においては、香港が依然として地域貿易拠点となっている。
• 在香港の日本企業は、米国の関税措置へのレジリエンスを示しており、回答企業の約4分の3が、最終的な収益への影響は軽微、または皆無と見込んでいる。
• 世界的な貿易の不確実性の高まりに対し、回答企業の約65%が様子見をしている。不確実性へのアクションプランを立案している回答企業のビジネス戦略としては
「China for China(中国市場向け中国国内生産)」が首位(23%)となっている。続いて新規市場への分散(15%)、香港の自由貿易港としての地位とCEPAを活用した中国本土へのアクセス(13%)が挙げられる。
• 世界的な貿易の不確実性が続く見通しの中で、在香港の日本企業のうち72%が、多くの国際市場、とりわけ ASEAN、中国本土、欧州において事業活動を拡大したい意向を示した。
• 回答企業の60%近くが香港内での事業を維持・拡大したいと回答し、中国本土での事業における高い戦略的重要性(38%)、調達・販売・サプライチェーン再構築における地域統括・管理拠点としての役割(37%)、東南アジアにおける地域事業の戦略的重要性(30%)を挙げた。
• 日本企業は香港を、事業活動推進のための強固なビジネス拠点として評価している。特に世界的な貿易の不確実性を背景として、現在および将来的な事業活動を推進できることが香港の主な強みであり、10ポイント中7.5ポイントという高い平均スコアを獲得している。
香港は長年に亘り、日本企業にとっての重要なビジネス拠点であり、海外、特にアジア太平洋地域において事業を管理・拡大するための役割を担ってきた。2024 年時点で、1,430 の日本企業が香港に地域本部・事業所を有しており[1]、2018 年の 1,393社から増加している。
近年、世界的な貿易やビジネスの見通しはより不透明さを増している。米国政府が導入した(または導入すると迫った)新たな輸入関税率により、企業は事業戦略の適応とサプライチェーンの再考を迫られている。
このような背景のもと、2025年7月14日から8月1日にかけて、香港貿易発展局研究部は、香港に拠点を置く日本企業を対象にオンライン調査を実施した。本調査は米国と他の国々との貿易協定が正式に発表される前に実施されており、米国の関税と世界的な貿易の不確実性がそれらの企業にどのような影響を与えるのかを評価することを目的としていた。加えて、各企業の関税に対応するための戦略を明確に理解するとともに、ビジネスハブとしての香港が、この不確実性にどう対処できるのかを把握するという狙いもあった。アンケートは431社に配布され、107件の有効な回答が得られた。
回答の大半は米国と他国との貿易協定が発表される前に寄せられたため、不確実性の緩和に起因したポジティブな意識を、十分に捉えきれていない結果となっている可能性がある。米国は主要な貿易相手国との間で、4月の発表よりも低い関税率とする貿易協定に合意した。更に、中国本土と米国の貿易協議は90日間延長され、11月初旬まで継続されることとなった。これにより、2025年6月11日に合意された二国間貿易協定について更なる交渉が可能となった。こうした明るい兆しは、グローバルビジネスを取り巻く状況の幸先が良いことを示している。
一般的に、日本企業は香港の拠点を活用して、香港現地外の市場におけるビジネスを管理している。グレーターベイエリア(GBA)およびASEAN地域は事業活動を行う上で特に重要なエリアである。全体として、回答企業の約 80%が、現在購買・販
売を行う拠点として香港を利用していると回答した。アジア太平洋地域の他の主要市場については、回答企業のうち86%が中国本土と、70%がASEAN地域とビジネスを行っていると報告している。一方で、韓国・オーストラリア・ニュージーランドといったその他主要アジア太平洋地域(APAC)の経済圏と取引を行っているのは33%にとどまっている。